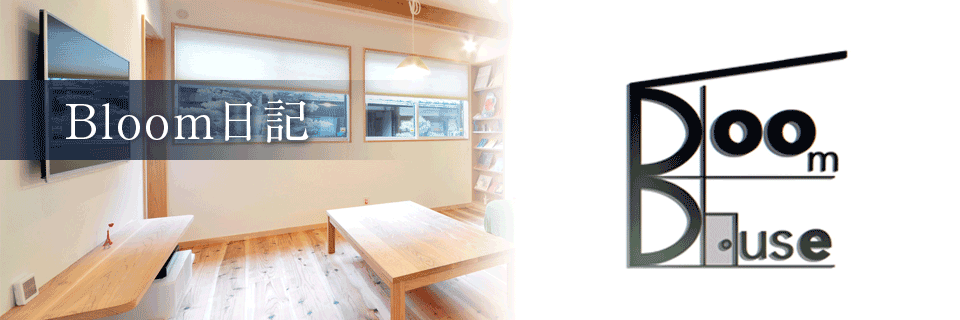浮かせる収納!!
皆様、明けましておめでとうございます!
本年も宜しくお願い致します_(._.)_
ご無沙汰しておりました。。横田です!
随分と間があいてしまいました。。
さてさて、今回は「浮かせる収納」について話してみます!
みなさん、日々のお掃除できていますか?
特に年末の大掃除も大変ですよね?
賃貸でも、戸建でも、せっかく住んでいるのだから、
綺麗にしておきたいとみんな思いますよね?
「綺麗に使いたいとは思っているんだけど、掃除が大の苦手で...」
「仕事が忙しくて、片づける時間が取れない...」
こんな風に思ってしまう私のような人も少なくないと思います!
今回は私と同じようなお悩みを抱えている方に、
日々のお掃除が続けられるおすすめの方法をご紹介します!!
その方法は!!
「浮かせる収納」です!
浮かせる収納は、以前流行っていたので、
ご存じの方もいるかもしれません。
「浮かせる収納」の良さは、
" 毎日の掃除が簡単になること " です!
掃除をする際にお風呂場とキッチンの掃除が、
特にめんどくさいと感じる方も多いのではないでしょうか?
どちらも水回りということもあって、
「ぬめり」のお掃除が非常にめんどくさい。。。
毎日「ぬめり」を掃除するのもめんどくさいし、
かといって「ぬめり」を放置すると、においが気になったり、
頑固な汚れになったりと百害あって一利なしですよね。
そんな「ぬめり」ですが、水回りの浮かせる収納では、
この「ぬめり」というキーワードが非常に重要になってきます!
結論からお伝えすると、「浮かせる収納」をすれば、
「ぬめり」とおさらばできるのです!
調理器具や洗面用具を浮かせることで、
水が溜まらず清潔を保つことができるため、
「ぬめり」の発生を抑制することができます!
他にも、浮かせる収納をすることで、
ロボット掃除機や床拭きロボットをはじめとした、
便利家電を使用しやすくなるため、お掃除する頻度が増え、
部屋をきれいな状態に保ちやすいという効果もあります!!
ちなみに私の家では、
・歯磨き粉と歯ブラシ
・調理器具
・食器洗いスポンジ
・シャンプー、ボディソープ
などを浮かせています!
100円ショップなんかにも置いていて、
少額からでもそろえやすいので是非試してみてください!
現代は情報社会ということもあり、
YoutubeやTwitterなど、様々な媒体で
「浮かせる収納」についての情報がたくさんでてきます!
日々の掃除を少しでもお手軽にするために、
「浮かせる収納」を始めてみてはいかかでしょうか?
それではまた!
ありがとうございました!
「笑え!」「遊べ!」自分らしい1日を!